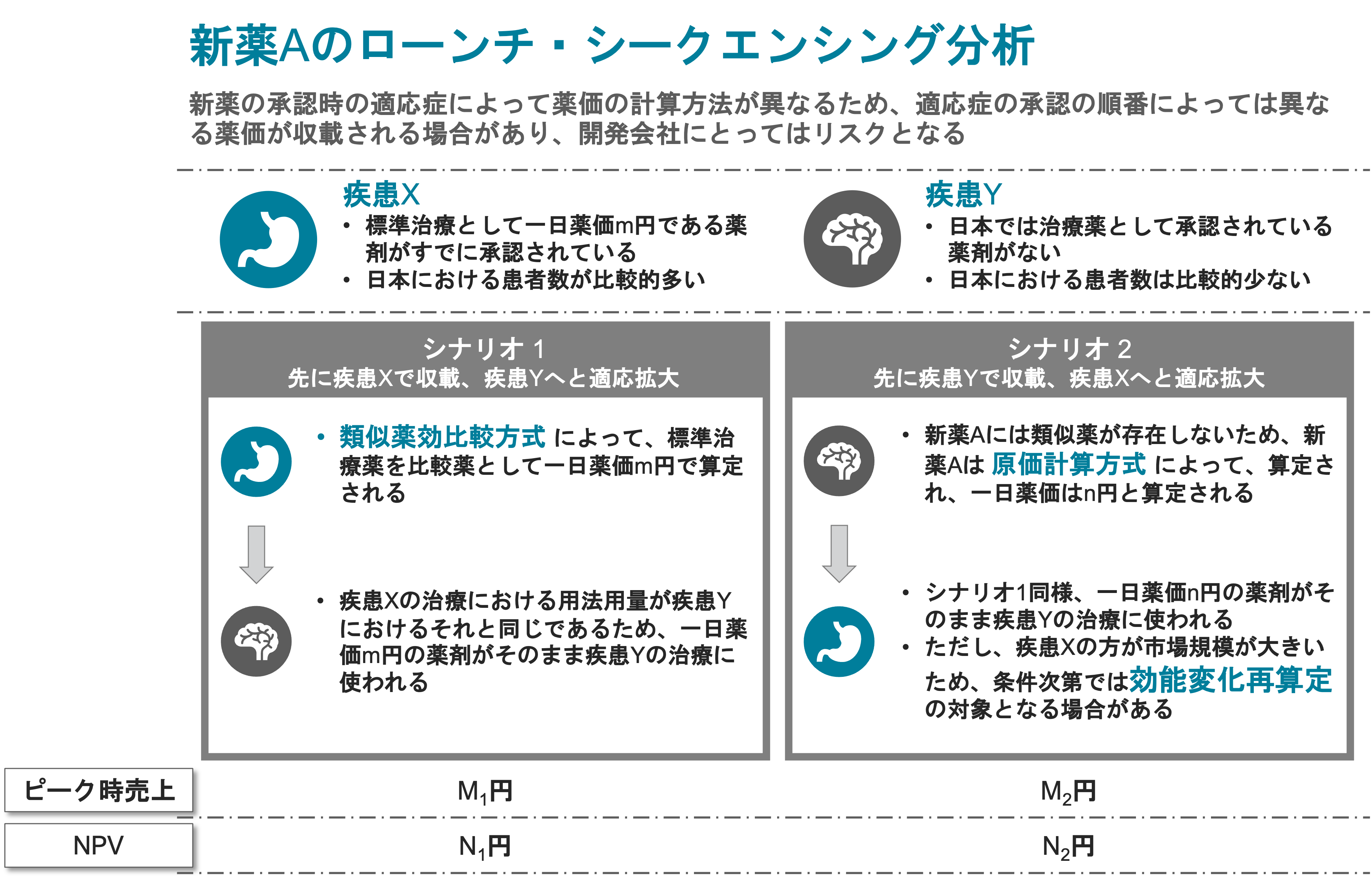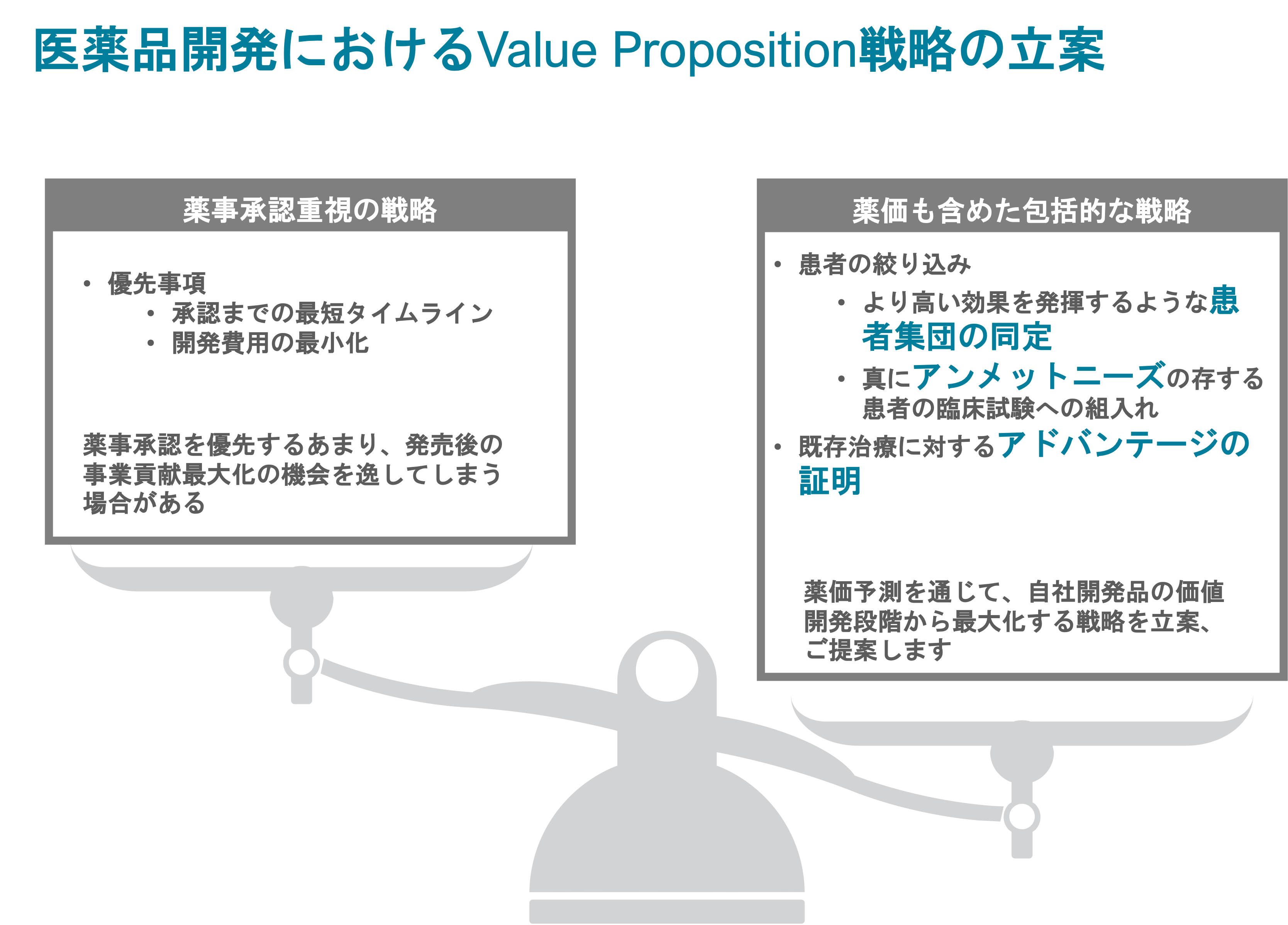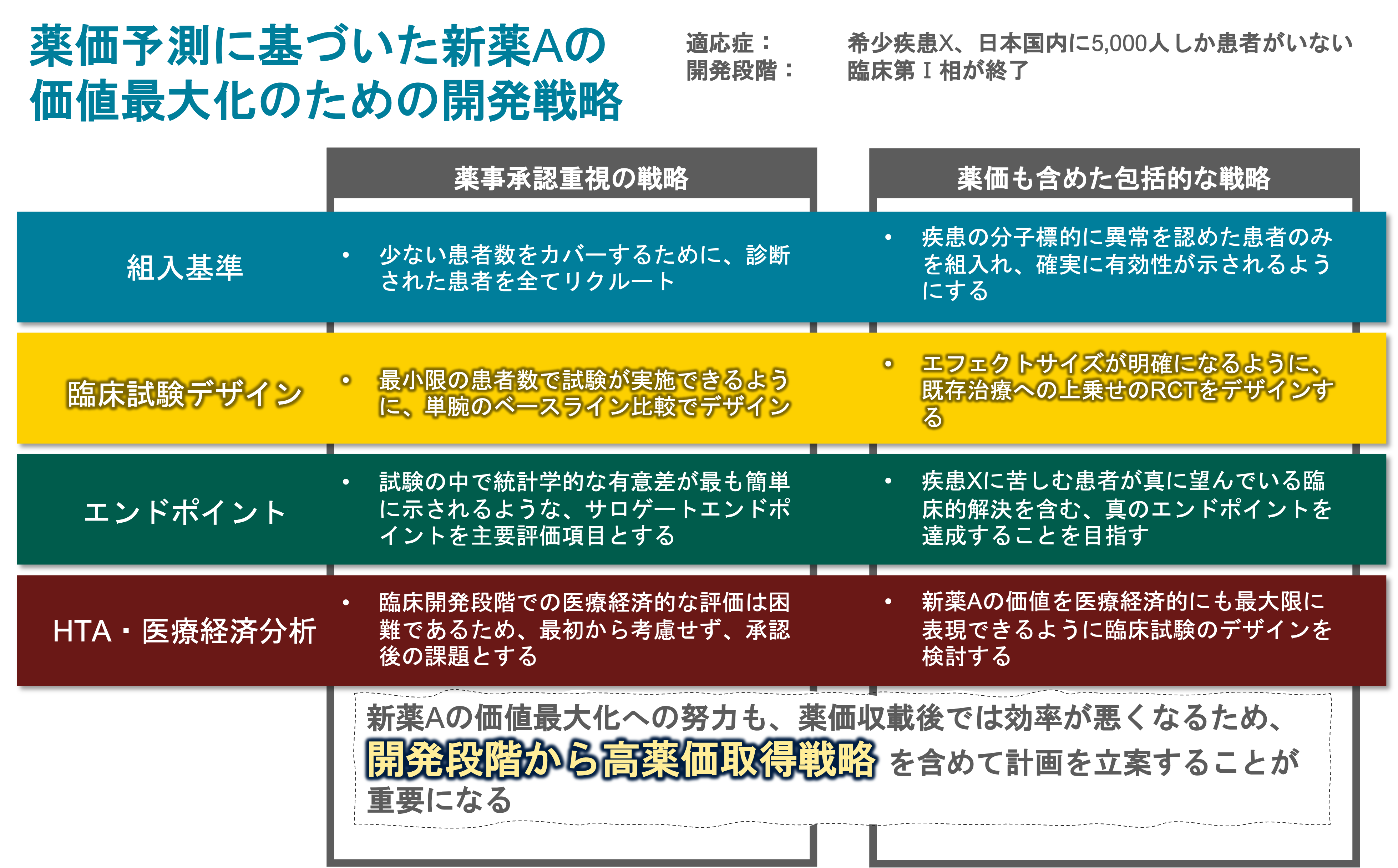連載:医薬品の事業性評価の理論と応用
『事業性評価の目的と意義』
医薬品の事業性評価の特徴と注意点(2)
2022年1月24日〈通巻第1194号〉
「マーケットアクセス」という言葉がある。2010年代から医薬品産業においてよく使われるようになったバズワード(流行りの業界用語)であるが、医薬品の文脈でこの言葉に定義を与えるとすれば、マーケットアクセス戦略とは「ある製品の保険償還および臨床的な使用制限の条件をなるべく良いものにすることによって、一方ではその製品がもたらす単位当たりの利益がより大きくなるようにし、他方ではより多くの患者にその製品が使われるようにし、併せてその製品の価値最大化を図る戦略」であると言い換えることができるであろう。医薬品以外の財においてはmarketaccessという言葉は通常、製品の国際展開、新規市場参入における様々な障壁を取り除くことを言うことが多いが、上述のように医薬品の場合はかなり違う意味合いで使われている。これは、特に先進国の間では医療用医薬品が保険償還の対象となっていることと深く関連しており、このために医療用医薬品市場においては「購買主体が分離している」という状況となっている。そのことこそが、医薬品と他の財との、財としての性質が際立って異なっている部分であると言える。
既に見てきたように、医薬品の財としての特徴の一つは、それが満たそうとする欲求ニーズの必須性、緊急性の高さにある。したがって、医薬品による医療サービスの提供は基本的人権のうちの生存権に含まれ、わが国においては国家による社会福祉の一環として、医療サービスを必要としている国民すべてに、そのサービスは平等に給付されるべきものと考えられている。医薬品によるものを含む医療サービスは、日本においては現物給付という形で直接提供される。また、医師法第19条に、いわゆる医師の応召義務が規定されており、医業報酬が不払であっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできないと解されている。日本国民はその経済的な能力に大きく左右されることなく、必要に応じて医療サービスの提供を受けることができるということが、様々な政策を通じて実現されている。そしてそれらの政策の中核に据えられているのが、いわゆる国民皆保険制度なのである。日本の医療制度の詳細について語ることは筆者の手に余ることであるが、医薬品の事業性評価と密接に関連がある点としては、既に述べた購買主体が分離されているという点についてまずは考察を加え、そこから派生する重要な論点をいくつかピックアップして議論してゆこう。
購買主体の分離
例えば自動車(自家用車)のような一般的な財について、その購買の意思決定のプロセスについて考えてみると、その費用を支払うのも、どのような自動車を購入するかということを選ぶのも、そして実際にその自動車に乗るのも、同じ個人、同じ主体であることが普通であろう。したがって、自分の好みや家計の状況、自分にとっての自動車の必要性などにあわせて、費用と自動車の性能などの効用とのバランスを見極めながら、どの自動車を購入するのかということについて判断を下すことになるだろう(図1)。ところが医薬品の場合、特に医療用医薬品の場合、そして特に先進国の場合にはその意思決定プロセスは必ずしもそのようにはなっていない。患者に対して医療用医薬品が処方される場合であっても、どのような医薬品が処方されるのかということについて選択を行うのは、専門家たる医師である。さらに、多くの場合には医療費の少なくとも一部は保険者が負担する。患者は基本的には医療サービスの提供を受けそれを消費する主体となるにすぎない。このように医療用医薬品によるサービスの提供に関しては費用負担の主体、選択の主体、そしてサービスの消費主体とが一つの個人の中に共存しているのではなく、分離されてるいことがその大きな特徴であると言えるだろう。このことこそが、社会全体でリスクをシェアすることで、患者が支払う医療費の自己負担額が軽減され、国民に対して良質かつ高度な医療を受ける機会を平等に保証する仕組みであるところの国民皆保険制度の本質的な部分そのものであると言える。このような意思決定主体の分離がもたらす影響について、ここではいくつかの切り口から考察を加えてみたい。

ミクロ経済学的な考察
主体の分離がもたらす影響を考察するにあたっての重要な切り口の一つはミクロ経済学的な分析ではないだろうか。消費者と企業とが互いに合理的な行動を取ることによって総余剰が最大化するという市場均衡モデルは、消費者において消費主体と費用負担主体とが分離している場合には、どのように修正されるべきだろうか。併せて国民皆保険の前提の一つである医薬品へのアクセスの確保が合理的な企業行動に与える影響についても考察する。
市場均衡モデルの修正

一般的な市場均衡モデル(図2)においては、消費者は価格に応じて需要量を決定し、需要の法則にしたがって価格が下落すれば需要量は増加する。一方、生産者は価格に応じて供給量を決定し、供給の法則にしたがって価格が下落すれば供給量は減少する。供給量と需要量とは価格を仲立ちとしてそれぞれが一致する均衡取引量に到達する。このように、価格が需要と供給とにしたがって自由に変動するという働きが、市場を均衡に向かわせ、両者にとっての余剰を最大化する。この一般的な市場均衡モデルは、財が医療用医薬品である場合においてはどのように修正されるべきであろうか。市場均衡モデルの前提に対して影響を与え得る医療用医薬品市場に固有な性質は以下ようなものであろう。
- 消費者行動においては、患者における需要の価格弾力性は低い。医薬品の特性である必須性・緊急性の高さや代替財の無さに加えて、健康保険に加入している場合には自己負担が限られていることにもよる。
- 企業行動においては、製薬企業に対しては医薬品の安定供給が義務付けられており、価格とは無関係に全需要を満たすように供給を行う。
- 価格は公定価格であり、需要と供給とに従って変動はしない。
この3つの性質のために、医薬品の需要と供給との関係には以下のような修正を加えるべきではなかろうか。
- 需要曲線の傾きは大きくなる。
- 供給曲線は、企業は価格に応じて供給量を決定できないためにその関係性を表現している供給曲線は概念できない。供給量と限界費用との関係を示した限界費用曲線は依然として概念できる。
- 価格に需要と供給との調整機能はなく、市場は均衡していないため均衡価格は概念できない。公定価格と公定価格に対して比例する患者自己負担額が概念できる。
「ボリュームテイカー」と公定価格

この結果、医薬品のミクロ経済学的なモデルは図3のように表現できる。この特徴としては、一つには取引量は患者自己負担額と需要曲線との交点によって与えられることで、ここには企業行動の関与する要素はない。すなわち、企業は価格だけでなく、供給量も受け入れなければならず、プライステイカーであるだけでなくいわばボリュームテイカーでもあるという立場が表現されている。また、患者自己負担額が十分低ければ、ほとんどの消費者は薬剤を手にすることができることを示している。これは、限界費用曲線と需要曲線との交点(ここでは仮に「元の市場均衡点」と呼んでおく)における「元の均衡取引量」よりも多い取引量が供給されることを示しており、医薬品へのアクセスが保険政策によって、市場の手に委ねるよりも改善されることを示している。【図3】
一方、公定価格は「元の市場均衡点」における「元の均衡価格」よりも十分に高く設定されている。これは、そのような公定価格が限界費用曲線よりも低い状況では製薬企業が医薬品の供給というビジネスから撤退してしまうためであり、これでは医薬品へのアクセスという観点からは元も子もない。逆に言えば、薬価の算定法としての原価計算方式は、公定価格を限界費用曲線に対して相対的に決定しようとする試みであり、考え方としては合理的なのである。
医薬品市場の消費者余剰と生産者余剰
余剰はどのようになるだろうか。需要曲線の左、患者自己負担額の上の面が医薬品の消費者余剰となるが、これは「元の均衡価格」と患者自己負担額との差の分だけ大きくなっており、患者負担の軽減とアクセスの改善とによってもたらされている。一方で、生産者余剰は限界費用曲線の左で、公定価格(実際には薬価ではなく、いわゆる工場出荷価格であるべきだがここでは問題にしない)の下の部分であるが、公定価格が「元の均衡価格」よりも高いことによる差分とアクセスの改善とによって増加している。このように、消費者余剰と生産者余剰とは重なっている部分があると考えられ、この部分は公定価格と自己負担額との差分であるために、これを健康保険の保険者が負担していると考えられる。すなわち、保険者は加入者の医薬品へのアクセスを改善するにために、自らの負担によって消費者と生産者とに対して余剰を提供している、とこの図から解釈することができる。【図4, 5, 6】



保険者負担と死荷重
保険者負担分はこの公定価格と自己負担額との差分と、取引量との積として表されるが、ここには消費者余剰にも生産者余剰にも含まれない死荷重の部分が生じている。これは「元の市場均衡点」で市場が均衡していた場合であれば、消費者の立場からは元の均衡価格であれば医薬品を購入しなかったであろう人の支払意志(willingness to pay; WTP)の部分と、生産者の立場からは「元の均衡取引量」で生産していたのであれば最大化していたはずの利潤が、多く生産してしまったために失われてしまった部分とを示している。費用負担主体とサービス消費主体とが分離することによって、このような非効率が発生してしまうのである。
「高薬価による恩恵」と安定供給義務
さて、このミクロ経済学的な考察はいくつかの興味深い示唆を含んでいる。一つには、上述の通り製薬企業は自らが供給する財である医薬品については価格も供給量も自分で決められない。しかし、公的医療保険制度の目的である、医薬品を含む医療サービスへの国民の十分なアクセスを確保するためには、そもそも営利企業である製薬企業が医薬品を生産し、供給をしてくれなければならない。したがって国家としては、製薬企業がプライステイカーであるだけでなくボリュームテイカーであるという条件に甘んじていてなお医薬品を生産、供給してくれるだけの十分なインセンティブを付与しなければならない。それは実際には、公定価格である薬価が十分なマージンを製薬企業に保証することを通じて行われている。図5の「高薬価による恩恵」の矢印として示されている部分にそれが示されている。「高薬価による恩恵」の部分の生産者余剰は「元の市場均衡点」で市場が均衡していたとしたときには得られていなかった余剰であり、これが公的価格が設定されていることによって企業の取り分として許容されているのである。逆に言えば、医療用医薬品のビジネスモデルにおいては、医薬品が公的医療保険制度の枠内に含まれ、十分なマージンを許された状態で取引ができることが極めて重要であるということが、ミクロ経済学的な切り口からも改めて確認できるのである。
一方で、公的医療保険は社会全体でのリスクシェアリングの仕組みであるため、保険加入者が保険料を支払うことによって成立している。上述の「高薬価による恩恵」の生産者余剰も、直接的にはすべて保険者が負担している(図5及び6参照)が、それは間接的には加入者の保険料を原資としている。したがって、医療用医薬品を扱う製薬企業は間接的に社会全体によって助成されている企業であると言え、それは社会全体が製薬企業の、医療用医薬品の安定供給というサービスに対する期待を表現しているとも考えられるのである。
情報の非対称性と逆選抜
さて、ここでもう一つ見逃せない重要な視点がある。公定価格を決める当局であっても、それぞれの医療用医薬品の限界費用曲線について、必ずしも理解しているわけではない。すなわち、製品たる医薬品の原価については製薬企業と当局との間には情報の非対称性が存在するのである。当局には製薬企業が十分「高薬価による恩恵」に浴することができ、日本国内での安定供給義務を果たしてくれるような生産者余剰に浴することを許容しつつも、予算制約がある中で薬価をなるべく低く抑えたいという難しい課題がある。一方、製薬企業側はこの非対称な状況を利用して自らの利潤を最大化させたいという動機が働いてしまう。医薬品開発には莫大な費用がかかるという印象を社会全体に持たせ、高薬価が許容されるような心理的状況を作り出すことや、たとえばバイオ医薬品などの特定の医薬品の製造原価が他のものよりも高いかのような印象を持たせると言ったような、いわばブランド戦略を取る動機が形成され得る。
このような情報の非対称性は結果として、例えば薬価収載の見送りのような、いわゆる逆選抜的な状況を招いてしまう場合がある。

参考資料
神取道宏.2014. ミクロ経済学の力. 東京: 日本評論社
小黒一正, 菅原琢磨. 2018. 薬価の経済学. 東京: 日本経済新聞出版社
平成24年厚生労働白書. https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/12/
Acemoglu, Laibson, and List. 2016. Microeconomics (Global Edition).Harlow: Pearson.