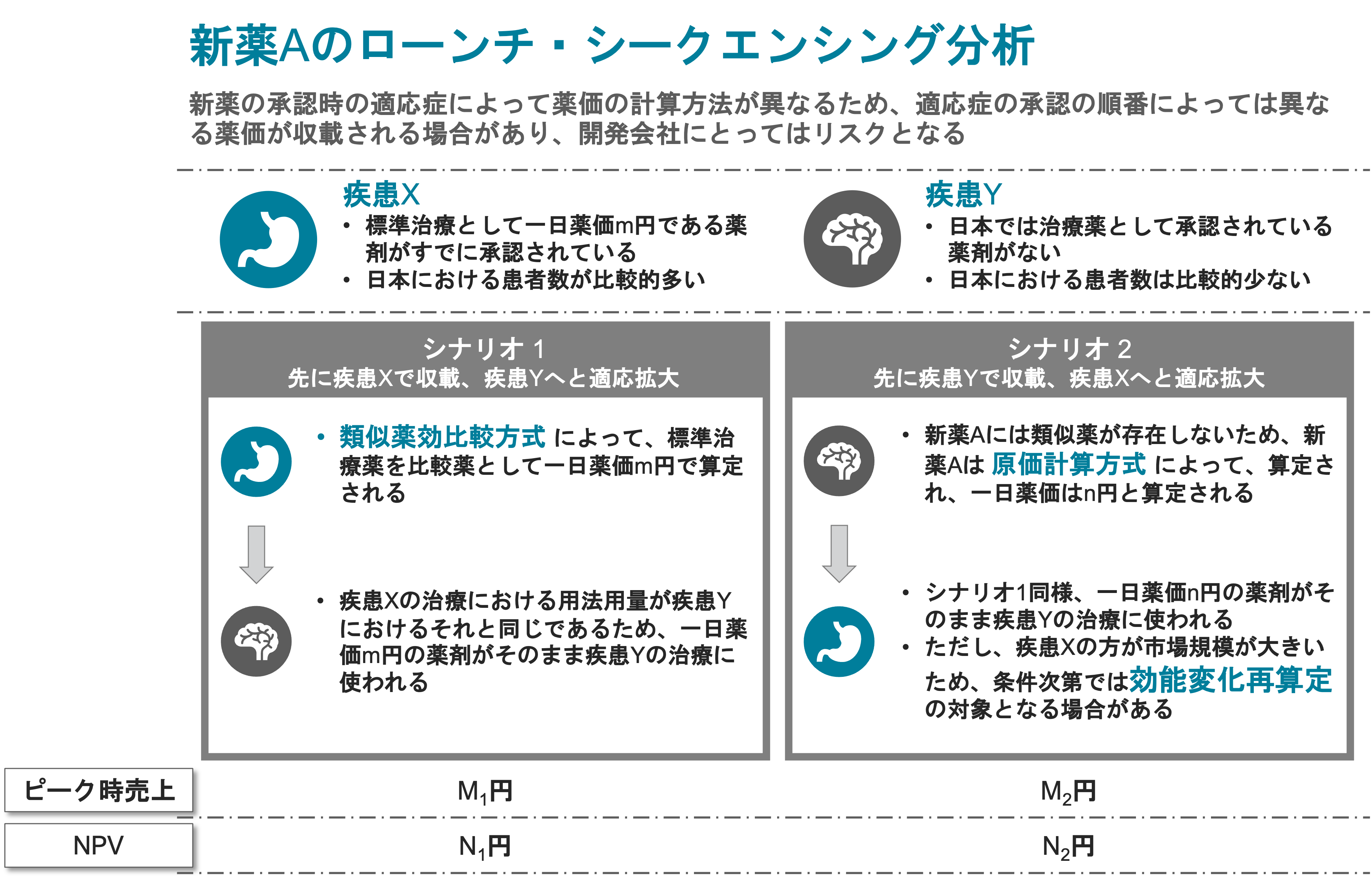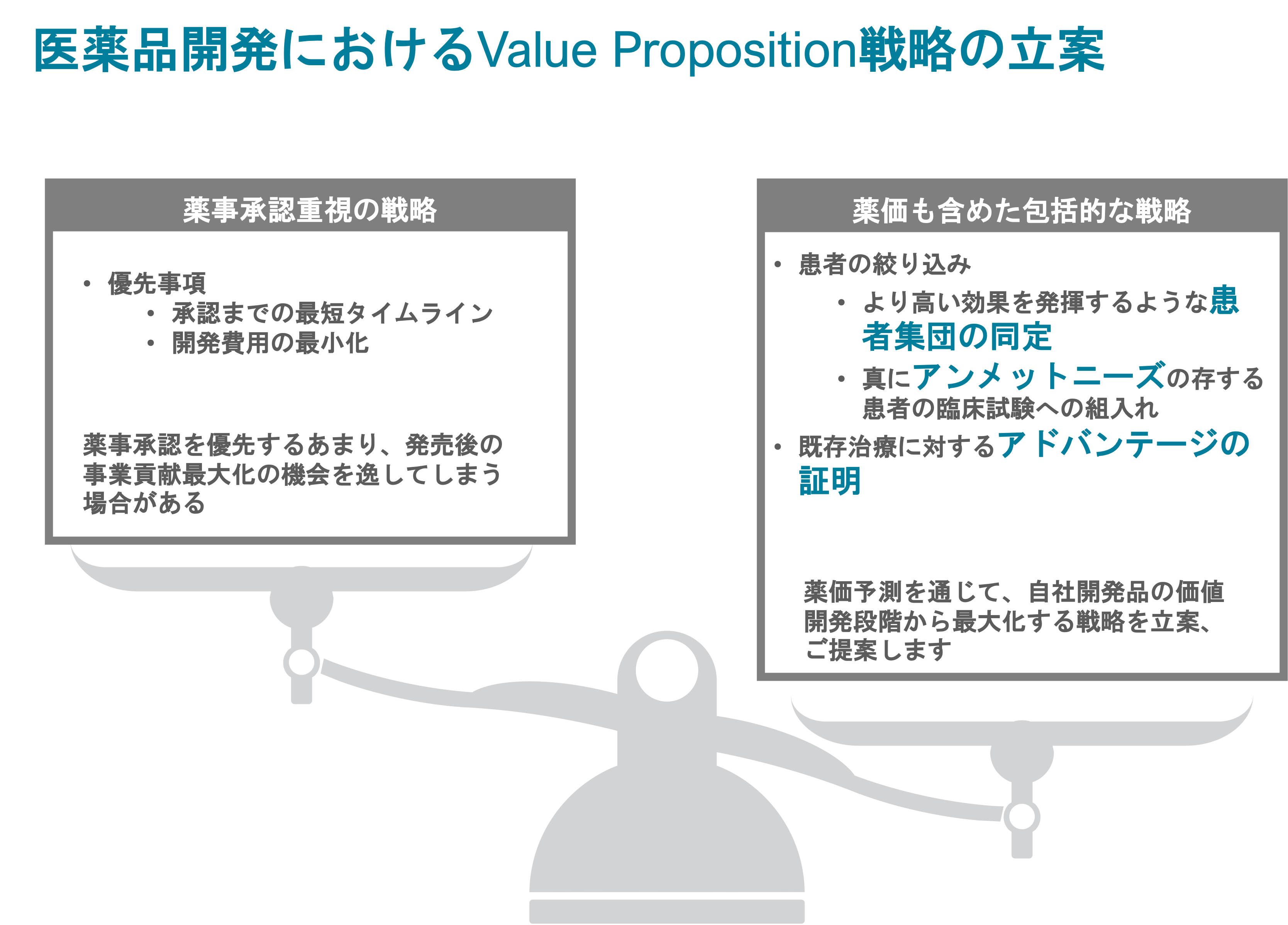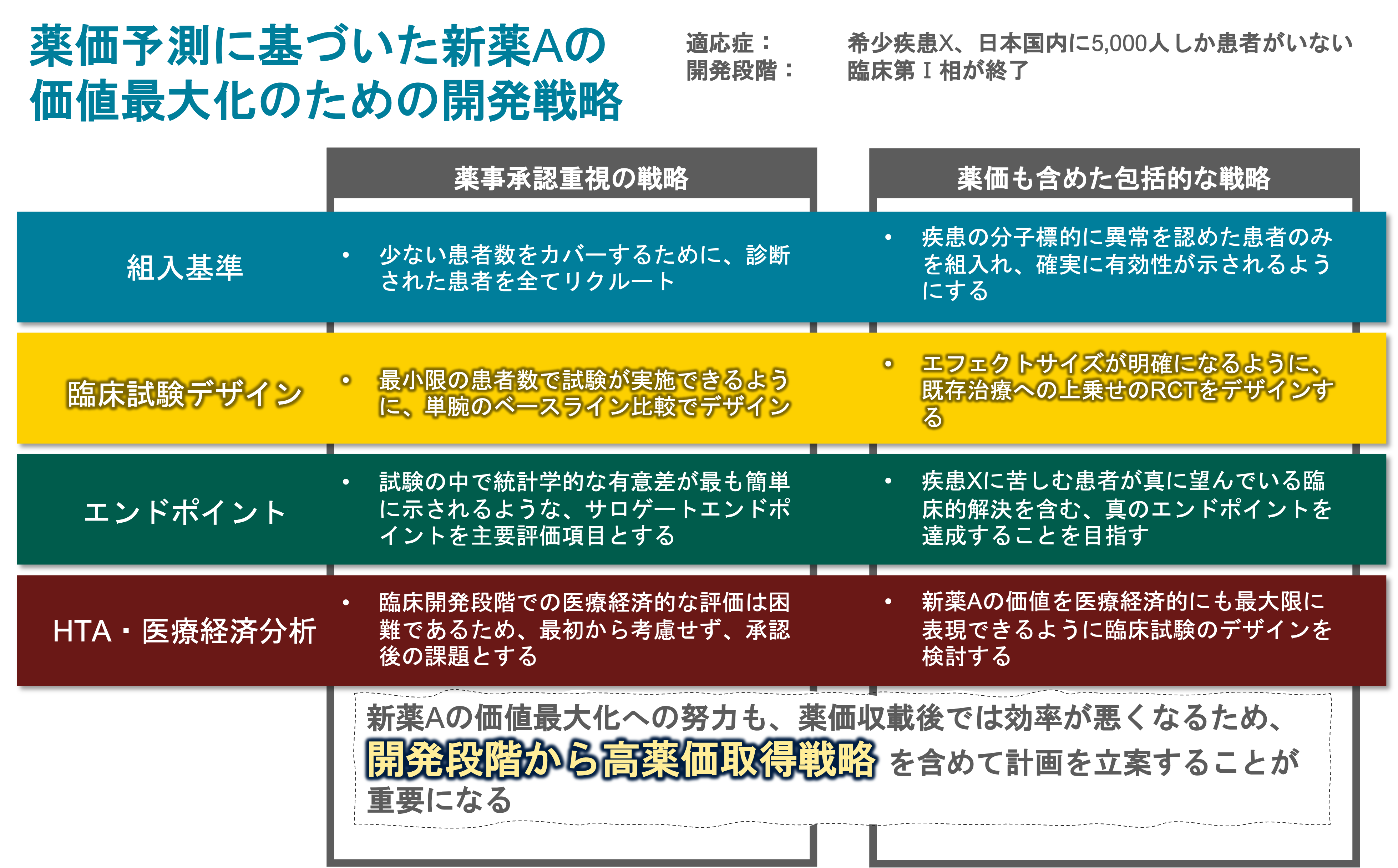ロバートAスワンソンとジェネンテックの成功

Robert A. Swanson
今年、2021年はバイオテクノロジー産業が誕生してから45年目という節目の年である。ちょうど45年前の1976年1月17日に(本稿は1月13日に書いている)、新進気鋭の実業家ロバート・スワンソンと分子生物学者ハーバート・ボイヤーとは、カリフォルニア大学サンフランシスコ校のボイヤーのオフィスで初めて面談した。この二人の出会いが、バイオテクノロジー産業を切り開いたベンチャー企業、ジェネンテックの誕生をもたらしたのである。この時、スワンソンは若干28歳。ジェネンテックの業績はもちろんボイヤーとCity of Hope National Medical Centerのアーサー・リグスおよび板倉啓壱に率いられた研究者集団の、最先端の研究業績によってけん引されたのであるが、それを実現せしめたのはスワンソンの経営手腕であるといってもよい。スワンソンは、最先端の生物学の業績を事業化するという、当時としては画期的なビジネスモデルを実現させたのである。1970年代の当時、基礎科学のビジネス化はそもそもの実施可能性という課題に加えて、アカデミアの民間資金に対する強い忌避感もあり、非常に難しいと考えられていた。それを乗り越えて、今日ではわが国でも当たり前になってきている大学の研究業績の民間企業へのライセンスモデルを構築して、一大産業の基礎を築いたスワンソンの語録から、今日のバイオテクノロジー産業に十分に当てはまるようなエッセンスを論じてみたい。
“バイオテクノロジーの分野においては、製品と基礎科学との垣根はそれほど高くない”
ジェネンテックの創業当初のビジネスは、インビトロで合成したDNAを用いて、大腸菌の系で発現させたペプチドを抽出して医薬品を製造するというシステムであった。当時はいわゆる生物学のセントラルドグマにかかわる「分子生物学」は基礎研究に分類される分野であり、また、cDNAによる発現系もまだ未成熟な状態にあったことから、こういう実験系において発現されたペプチドを回収して医薬品として応用するなどということはかなり遠い将来のことであると考えられていたようだ。
2021年の現在においては、もはや医学・生物学分野の研究であって医薬品・医療機器としての応用の可能性を標榜しないような学問分野は、大きな投資は期待できない状況になっているといっても過言ではない。ノーベル医学生理学賞の受賞のトレンドを見てもそれは明らかである。しかし、ほんの数十年前にはアメリカの西海岸の大学でさえ、そういう状況にはなかった。そこには、公的資金で賄われている大学の研究に民間企業が入ってくることを嫌悪する、アカデミアの閉鎖的な雰囲気があった。スワンソン自身も、ボイヤーや他の研究者が、大学での職がありながらジェネンテックにも所属して、研究の時間を民間企業に割いていることに関して強い風当たりがあったことを認識していた。そのために、スワンソンは、ジェネンテックに所属する研究者はそこでの研究成果を自由に論文化してもかまわないというポリシーを取っていた。スワンソン自身は豊富な資金と自由な風土とがあれば、研究者はむしろ民間企業であるジェネンテックの研究所にいた方が成果はより多く上げられると考えていたようである。
一方、スワンソンは大学から研究成果の権利をライセンスするときには、独占的ライセンスにこだわった。スワンソンは大学の研究は独占的に事業化されて初めて価値を社会に還元できると信じていた。スワンソンはペニシリンの普及が遅れたのは発見者のフレミングがそれを特許しなかったことが一つの要因であるという逸話を折に触れて引用した。
“これはビジネスになると思う”とスワンソンが提案し、ボイヤーは”そうかもしれない”と応えたことによってジェネンテックは始まった。基礎研究といえども、製品化へのプロセスを常に考えておくことによってブレイクスルーはもたらされるのかもしれない。
“ハーブ(ボイヤー)は科学的実現可能性について明確な視座を持っていた。これは頑張れば実現できる、これは難しい。その見極めは(ジェネンテックのビジネスにとって)極めて重要だった”
「目利き」という言葉は人口に膾炙しているが、投資対象のプロジェクトの選択の基準や方法はビジネスにおける一般的な課題である。医薬品の場合は商業的に成功するかどうかということに加えて、開発がうまくいくかどうかということについて考える必要があるので、「目利き」は一層重要である。「目利き」の問題は規模が大きい製薬企業においては、実施するプロジェクトの母数を増やしてどれかは成功するようにするという物量的アプローチと、これらの数多くのプロジェクトを組織として経験することによって、いわゆる「経験知」を組織の中に蓄積してゆくという二つのアプローチの組み合わせで対応しているようだ。一方で、より規模の小さい企業においては、目利きは属人的なケイパビリティとなるだろう。
スワンソンはその意味ではボイヤーに対して全面的な信頼を置いていたようである。今では一般的となったcDNAではなく、インビトロでのDNA合成に基づいた発現系の構築を進めたのもボイヤーであるようだ。合成DNAは、当時の技術ではそこまで長いものは作ることが出来なかったため、当初の計画では最初の製品はインスリンとなる予定であったものを、よりアミノ酸残基が少ないソマトスタチンにすることも最終的にはボイヤーの判断だったようである。最初の小さな成功が、のちの大成功を導いたと考えることもできる。
“研究者を経営判断に関与させること。これは極めて重要なことだ。研究者は、確かにビジネスのことには明るくないかもしれない。しかし、彼らは基本的に頭が良く、そして鋭い、的を射た質問をすることがある。”
スワンソンはボイヤーに限らず、自分が雇った研究者たちを心から信頼していた。また研究者たちの素朴な疑問も歓迎する態度を取っていた。ある時、ある研究者が「なぜそんなに儲ける必要があるのか?」と質問をした。それに対してスワンソンはこう答えたという。「つまり、顧客が求めているものを届けていることが儲かるということなんだ。薬を作るためにかかる費用以上のお金を顧客が払ってくれるから儲けになる。儲けとは、顧客を知ることなんだ」
“自分が理解できないものについては、やらなかった”
スワンソンはMITスローンのビジネススクール出身で経営学修士を修めているが、学部もMITで化学出身であるから理系の素養も大いに持ち合わせていたようである。実際にはサイエンティフィックな議論についても極めて高いレベルで理解していた。サイエンスを理解し、それを説明できることは、ジェネンテックのようなバイオテック企業のマネジメントであれば当然のことであるといえる。
“(ジェネンテックをフラットでオープンな組織にすることについて)極めて意図的にそのようにしていた。それはハーブと私の企業哲学だった。そしてハーブがサイエンス、私がビジネスを担当して、それは完璧に織りなされた布のようだった”
さらには、自社株を従業員にも持たせるということもスワンソンのポリシーだった。従業員にビジネスのオーナーシップを持たせること、そして金銭的な動機付けをすることも重要だと考えていたようである。一方、研究室に頻繁に足を運び、研究の進捗を聞き、研究者を鼓舞することも大いにしていた。また、科学的な評価については専門家である研究者に一手に担わせる、実際に手を動かした者に成功の功績を与えるというのは一貫した企業哲学であったようだ。
“結局のところ、人は金銭だけでは動かないと思う”
“我々の研究者はいつも遅くまで研究室に残って仕事をしていた”
“いい仕事には、愛と情熱とが必要だ”
スワンソンはリーダーとして常に研究者と向き合い、研究の成果を理解し、それこそが会社の成功にとって必須であるということをよく理解していたのである。
“まずはモノありきだった” “創業当初から、自分たちの製品を自分たちで売れる、完全な製薬企業を一から作り上げるということが、我々の目標だった”
ジェネンテックにおいて、プロジェクトの選択基準として重視されたものの一つは、自販の可能性である。ジェネンテックが創業した1970年代は、「今から新しい完全な製薬企業を作り上げることは不可能だ」と思われていた時代だった。既存の製薬企業はあまりにも大きく、歴史があり、これらの企業と競合できるだけの競争力をつける会社を一から作り直すことは極めて困難であると考えられていたのである。しかし、スワンソンは自社で製品を販売することにこだわった。自らのテクノロジーによって生まれた製品は、自らで販売することによってはじめてそのテクノロジーのすべての価値を享受することができ、それによって新たなテクノロジーの開発に着手できると考えたのである。
しかし、メルクやリリーなどの大手がひしめく領域で、これらの企業を相手にとって正面から戦うことは望ましくない。当時、米国の医師の数は25万人もいると言われ、プライマリーケアの領域の製品を扱うべきではなかった。したがって、ジェネンテックの製品開発戦略はまずどの領域にモノを持ってくるかという、いわゆる疾患領域戦略であった。今では当たり前かもしれないが、少数のMRで回れる病院市場、スペシャリティ市場の製品を選んで開発するということの走りであった。
もう一つ重視したのは、開発のスピードである。開発が早いものとは、治験のエンドポイントが明確なもの。その基準で選ばれたのが当時は血糖が低下するかどうかということだけを見ればよかったインスリンである。多くのスタートアップ企業がそうであるように、ジェネンテックも創業当初はリスクを取って長期間に及ぶ開発プロジェクトを実施することはできなかった。これも、失敗すればおしまいのバイオテック企業ではなく、完全な製薬企業を作りたいというスワンソンの発想だった。
だが、スワンソン自身も認めているが、最終的には統一的な基準ですべてのプロジェクトのGo/no-goを決めているわけではなかった。実際にはそれは個別の案件ベースで決定されており、その基準が揺らぐことも多かったと語っている。
スワンソンは1999年に脳腫瘍のために52歳という若さで夭逝した。それから二十余年の月日が流れるが、スワンソンが作ったバイオテクノロジー産業はまだ脈々と息づいており、その産業から生まれた新型コロナウイルスに対するワクチンが、再び全人類を救おうとしている。